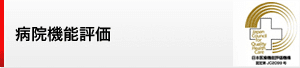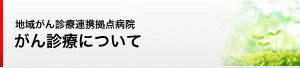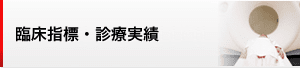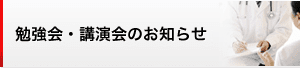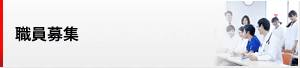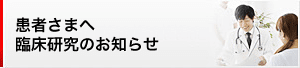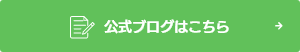消化器内科
消化器内科
当科は消化器外科と同一階(高層館8階)で消化器病センターとして診療しております。毎週行っている合同カンファレンスを通して、手術や化学療法が必要な 患者様には、消化器外科医師、放射線治療医師とも連携をとり、それぞれの患者様に適した質の高い集学的治療を心がけています。
また、日本消化器病学会・日本消化器内視鏡学会・日本肝臓学会・日本超音波医学会・日本消化管学会・日本カプセル内視鏡学会の専門医制度研修施設として、後進の指導育成にも力を入れています。
当科の紹介
- 外来診療
- 平日午前に2~3名の外来医を立て、紹介患者様の初診や治療中の再診患者様の診療にあたっています。外来化学療法の実施、各種専門領域の疾患についての相談にも積極的に取り組んでおります。
- 入院診療
- 消化器疾患を専門とする医師が主治医となり診療にあたっています。一般外来からの予定入院や、診療所や近隣医療施設から紹介される中等症あるいは重症患者様を積極的に受け入れ高度医療を提供します。
- 救急外来
- 救急外来担当医からの対診要請にもオンコール体制で即応し、24時間いつでも専門的な診療を提供します。
- 検査、治療
- 当科のスタッフは外来診療日を除き随時、内視鏡や超音波の検査や治療にあたっています。おこなった検査は全例スタッフで読影を行い、適切な診断を心がけるよう努めております。
診療実績
2021年1~12月 | 2022年1~12月 |
|
| 上部 | 5815件 | 6335件 |
| 食道EMR | 1件 | 5件 |
| (咽頭含)食道ESD | 29件(食道:25件,咽頭:4件) | 16件(食道:14件,咽頭:2件) |
| 胃EMR | 12件 | 18件 |
| 胃ESD | 51件 | 67件 |
| 十二指腸EMR | 8件 | 12件 |
| 下部 | 1383件 | 1449件 |
| EMR | 456件 | 437件 |
| ESD | 68件 | 41件 |
| ERCP | 218件 | 205件 |
当科で行っている治療
内視鏡的粘膜下層切開剥離術(endoscopic submucosal dissection:ESD)
従来行われてきた早期胃癌の内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection:EMR)は低侵襲性、機能温存を具現化した根治的癌治療法として定着していますが、問題点として不完全切除(分割切除)に伴う遺残・再発があり、その対策として確実な一括切除を行うべく内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が開発されました。現在、早期胃癌の内視鏡治療の中心となっていて、当院でも多くの治療を行っています。また、当院では胃にとどまらず、食道、大腸の病変にも積極的にESDを行っています。
ERCP関連
胆嚢結石症や総胆管結石症などの良性疾患は以前より頻度の高い疾患でしたが、最近は胆道や膵臓の悪性疾患が増加しています。当科では通常の内視鏡以外に超音波内視鏡(超音波装置のついた特殊な内視鏡)を用い、胆膵疾患の診断と治療にあたっています。
具体的には、巨大結石や積み上げ結石などの総胆管結石症の治療には外科的治療が必要でしたが、現在ではその多くを開腹手術することなく内視鏡で治療しております。悪性疾患に対しては超音波内視鏡にて進展度診断や穿刺吸引組織診にて確定診断を行い、進行癌に対してはステント留置を始めとする各種インターベンション治療、化学療法などに積極的に取り組んでいます。
● 胆道疾患に対する内視鏡検査( ERCP)に関する臨床研究のお知らせ
悪性消化管狭窄(食道、幽門・十二指腸、大腸)に対するステント留置術
消化器癌では、病状が進行したり外科的治療後に再発したりすると、消化管(食道、幽門・十二指腸、大腸)の内腔が狭くなる場合があります。このように狭くなった消化管内腔を「ステント」と呼ばれる医療器具を留置することで拡げるのが「ステント留置術」です。とくに大腸のステント治療については、「大腸ステント安全手技研究会」の主要メンバーとして、大腸ステント治療の安全確認や情報収集、他施設との共同研究など、全国規模での幅広い活動を展開しています。
カプセル内視鏡
胃十二指腸と大腸は通常、内視鏡にて観察可能ですが、胃と大腸の間にある小腸は本来観察が困難な部位でした。当科ではカプセル内視鏡を用い、小腸疾患の診断が可能となりました。診断に続き治療を行うためシングルバルーン内視鏡の導入を図ります。
C型慢性肝炎の薬物治療
C型慢性肝炎の治療は現在大きく変わってきています。これまではインターフェロンが使用されていましたが、副作用も強く、当院で治療を受けられた高齢の患者さんの多くが、途中で治療を断念されました。しかし、2014年9月からインターフェロンを使用しない治療、抗ウイルス剤を飲むだけの治療が新たに保険適応となりました。この治療はこれまでインターフェロン治療が行えなかった高齢者、基礎疾患(糖尿病やうつ病など)のある人にも高い治療効果を挙げ、副作用も少ないと報告されています。
2015年5月にはゲノタイプ2型の症例に、2015年9月にはゲノタイプ1型の症 例に新たな抗ウイルス剤が使用可能となりました。これまでは治りにくかったC型慢性肝炎が、3か月間きちんとお薬を飲むだけで、多くの人が治癒する時代に変化しています。一人一人の患者さんについて、現時点での肝臓の状態を確認させていただき、適切な治療法について一緒に考えていきます。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病など)に対する治療
大腸及び小腸の粘膜に慢性の炎症または潰瘍が生じる原因不明の疾患を総称して炎症性腸疾患といいます。その代表的な疾患が、潰瘍性大腸炎とクローン病です。潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができる病気で、クローン病は口から肛門にいたるどの消化管にもびらんや潰瘍ができますが、主に小腸と大腸を中心とし特に小腸末端部に好発する病気です。
その治療法は、栄養療法、内科治療、外科治療、内視鏡治療など多岐にわたります。内科治療としては、従来から使われている5-アミノサリチル酸製薬(ペンタサ、アサコールやサラゾピリン)、副腎皮質ステロイドや免疫調節薬(イムランなど)などの内服薬に加え、現在では抗TNFα受容体拮抗薬(レミケードやヒュミラ)やタクロリムス(プログラフ)が使用可能となりました。
当科では血球成分除去療法を交え、これらの組み合わせにより患者様一人一人に適切な寛解導入、寛解維持療法を提供できるよう積極的に取り組んでいます。
スタッフ紹介
消化器内科部 部長 兼 消化器センター長(内科)
1993年 島根医科大学卒
<資格等>
医学博士
日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会認定消化器病専門医、指導医
日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医、指導医
日本消化管学会認定胃腸科専門医、指導医
日本カプセル内視鏡学会専門医、指導医
臨床研修指導医
島根大学医学部臨床教授
<所属学会>
日本内科学会
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本消化管学会
日本膵臓学会
日本胆道学会
<専門分野>
消化器全般
副院長 兼 検査部長 兼 医療社会事業部 部長 兼 消化器内科部 医師
1989年 島根医科大学卒
医学博士
日本内科学会認定内科医
日本肝臓学会認定肝臓専門医、指導医
日本消化器病学会認定消化器病専門医、指導医
日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医、指導医
臨床研修指導医
島根大学医学部臨床教授
<所属学会>
日本肝臓学会
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本内科学会
<専門分野>
消化器(主に肝臓領域)
内視鏡科部 部長 兼 内視鏡検査室長 兼 消化器内科部 医師

1997年 島根医科大学卒
医学博士
日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会認定消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医、指導医
日本消化管学会認定胃腸科専門医
日本カプセル内視鏡学会専門医、指導医
臨床研修指導医
<所属学会>
日本内科学会
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本消化管学会
日本カプセル内視鏡学会
<専門分野>
消化器内視鏡:診断・治療、炎症性腸疾患
消化器内科部 副部長
2002年 島根医科大学卒
医学博士
日本内科学会認定内科医
日本肝臓学会認定肝臓専門医
臨床研修指導医
<所属学会>
日本内科学会
日本肝臓学会
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本超音波医学会
<専門分野>
消化器(主に肝臓領域)
消化器内科部 副部長
2004年 島根医科大学卒
医学博士
日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会認定消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医、指導医
臨床研修指導医
<所属学会>
日本内科学会
日本消化器病学会
日本内視鏡学会
<専門分野>
消化器全般
内視鏡科部 副部長 兼 消化器内科部 医師
2010年 岡山大学卒
日本消化器病学会認定消化器病専門医、指導医
<所属学会>
日本消化器内視鏡学会
消化器内科部 医師

2014年 島根大学卒
日本内科学会認定内科医
日本ヘリコバクター学会H.pylori(ピロリ菌)感染症認定医
<所属学会>
日本内科学会
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本消化管学会
<専門分野>
消化器
消化器内科部 医師
2019年 島根大学卒
<所属学会>
日本内科学会
消化器内科部 医師
2020年 島根大学卒
<所属学会>
日本内科学会